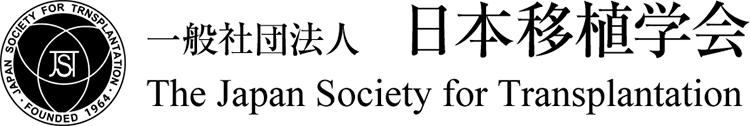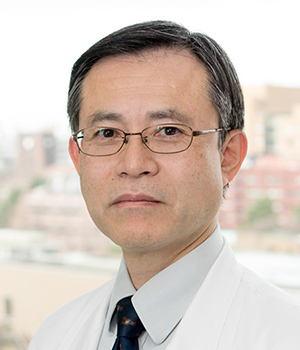理事長挨拶
江川前理事長を引き継ぎ、このたび理事長の職に就きました。私は心臓外科医としてこれまで25年間心臓移植の普及と成績向上に取り組んできました。胸部臓器移植を専門とする外科医が日本移植学会理事長となるのは初めてのことです。私が移植学会理事会に参画したのは2015年ですが、それより以前は心臓・肺移植の施行数は少なく、移植学会は腹部臓器移植の先生方を中心に運営されていました。臓器を超えて解決すべき問題は多くあり、江川前理事長体制では理事全員が心を1つにして課題解決に取り組んできたと感じています。私は学術・教育委員会委員長を8年間務めさせて頂きましたが、学術研究の推進と進化し続ける移植免疫の知識や移植関連技術の教育を通じて移植医療の安全性の向上と革新性の導入に貢献できたものと自負しています。改正臓器移植法施行5年後から心臓・肺移植は着実に増加し始め、胸部臓器特有の課題が浮き彫りになってきました。このような中、異なる臓器間の横の連携の重要性が認識されるようになり、移植学会においては専門となる臓器・分野を越えた風通しのよい関係性が構築されつつあります。
2023年は脳死臓器提供が歴史上初めて100例を超える記念すべき年となりました。日本移植学会は厚生労働省や日本臓器移植ネットワークなどと強力な協調体制を構築して、臓器提供の普及啓発とともに臓器提供可能な施設の支援と体制整備に注力してまいりました。臓器提供の増加はその成果であることは論を俟ちませんが、人口比で見てみると欧米諸国はおろか隣国の韓国や中国よりも依然として遥かに少ない状況です。単純に提供数が多いことがすべてではないものの、例えば心臓移植の待機期間が現在の5年超からせめても3年以内にすることは適切で安全な医療提供の観点から重要な責務であると感じています。今後とも臓器提供システムの向上と普及啓発に対して継続的な取組みが欠かせません。
2024年4月より医師の働き方改革が本格的に始まります。これまで現場任せになっていた医師の超過勤務の上限規制の導入と厳格化が課されます。日本移植学会では移植医の労働時間と労働環境の現状調査を行い、2022年学会誌「移植」に報告しました。そこで浮き彫りにされたのは過酷な労働環境とそれに見合わない待遇という問題点でありました。臓器提供は関係する多くのステークホルダーの弛まない努力によって増えてきましたが、移植施設側の体制整備が追い付いていない状況が明らかになってきました。本執行部において、移植施設の労働環境の改善ならびに個々の移植医の負担軽減を是非とも進めていかなければならいないと強く感じています。さらに、これまで以上に移植医療が働き甲斐のある魅力的な分野となるべく、将来を見据えて執行部一同心を一つに諸問題に取り組んでいく所存です。